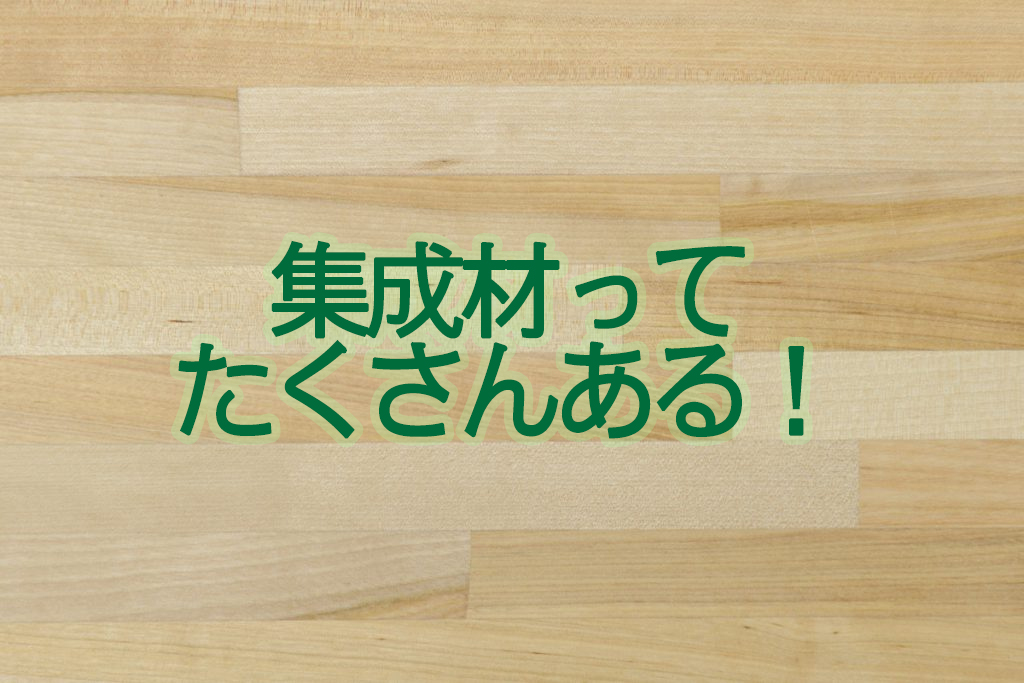住宅や家具、DIYの材料に欠かせない木材。なかでも、集成材は無垢材よりもコスパが高く、ホームセンターでも手軽に入手できるのが魅力です。
しかし、集成材の種類は豊富で、それぞれ特徴や強度が異なります。集成材を選ぶ際は、用途に応じて適切なものを選ぶことが大切です。
そこで、本記事では旭川家具に精通する木工のプロ「旭川木工センター」が、集成材の種類について詳しく解説します。
集成材の特徴やメリット・デメリットについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
集成材とは?集成材の定義と構造
集成材とは、原木から切り出した引き板や小角材を同一の繊維方向に重ね合わせ、接着剤で貼り合わせた木材のこと。加工する際に大きな節や切れ目などを取り除くため、無垢材に比べて品質が一定に保たれている点が特徴です。
なお、集成材を構成するひき板や小角材は、ラミナと呼ばれています。
集成材と無垢材の違い
無垢材は、ひとつの原木から切り出した木材のことを指します。集成材は小さく切った木材を接着剤で貼り合わせているのに対し、無垢材は接着などの加工を施していない点が大きな特徴です。
無垢材は、同じ樹種でも木目や質感、色合いなどにバラつきがあり、集成材に比べ価格が高い傾向にあります。
無垢材の魅力は、天然木の風合いを楽しめる点です。さらに、樹種によって木肌の色や木目、香り、手触りが異なるほか、さらに経年変化による色合いの変化も楽しめます。
他とは違う、木の個性や特性を活かしたオリジナルのデザインに仕上がる点も、無垢材ならではのメリットといえます。
集成材が使われる主な用途
集成材は「構造用集成材」と「造作用集成材」の2種類に大きく分かれ、それぞれ用途が異なります。
構造用集成材は国土交通省によって強度基準が決められており、寸法や面積に応じて大断面・中断面・小断面に区分されています。
中断面・小断面は、主に柱、梁、桁(けた)など木造住宅の構造部に、大断面は体育館や学校、集会施設などの大規模建築物に使われています。
一方、造作用集成材は、強度よりも仕上がりを重視して作られており、家具や住宅の内装に使われています。
集成材の種類と特徴
先ほども述べた通り、集成材には「構造用集成材」と「造作用集成材」の2種類がありますが、さらに日本農林規格(JAS)により、用途に応じて以下の4つに分かれます。
日本農林規格(JAS)による集成材の分類
| 種類 | 特徴 | 用途 | 使用される主な樹種 |
|---|---|---|---|
| 構造用集成材 | 建物の構造部に使用される集成材のこと。国土交通省によって強度基準が定められています。 | 建物の構造部(柱、梁、桁)体育館、学校、集会所、教会など | カラマツ、スギ、ベイマツ、スプルースなど |
| 化粧貼り構造用集成材 | 構造用集成材の表面に薄板を貼り付けた木材のこと。 | 和室などの在来軸組工法住宅の柱材(横断面の長さは90mm〜150mmに限る) | スギ、ヒノキ、エゾマツ、スプルースなど ※表面に使用される樹種 |
| 造作用集成材 | 集成材のうち、建物の内部造作に使われるもので、ラミナを素地のまま集成接着したものや、表面にみぞ切りなどの加工や塗装を施した木材のこと。 | 階段、壁、カウンター、床、家具など | 赤松、パイン、タモ、ナラ、ホワイトオークなど |
| 化粧貼り造作用集成材 | 造作用集成材に薄板を貼り付けたもの、またはこれらの表面にみぞ切りなどの加工や塗装を施した木材のこと。 | 和室の内装材(長押、敷居、鴨居など) | タモ、ナラ、ヒノキ、スギなど ※表面に使用される樹種 |
この他、集成材に似ている木材にはCLTとLVLがあります。どちらもラミナを接着する点は集成材と同じですが、接着方法が大きく異なります。
CLT(直交集成板)
CLTとは、ラミナを並べた後、繊維方向に対して垂直になるよう重ねて接着した大判の木質パネルのこと。ラミナを垂直方向に重ね合わせるため強度が高く、安定しやすいのがメリットです。
2016年4月、CLTの建築物への利用が制度的に認められ、CLTの普及と実用化が本格的に始まりました。主な用途には、住宅の床や壁、屋根などがあげられます。
LVL(単板積層材)
LVLとは、ロータリーレースやスライサーで2〜4mmにスライスしたラミナを、繊維方向が平行になるように重ね、接着剤を塗布し、高温・高圧で接着した建材のこと。集成材よりも強度が安定しており、住宅の柱や梁、家具など、幅広い用途に使われています。
集成材のメリット・デメリット
- 反り・収縮・膨張が起こりにくく、施工後のトラブルが少ない
- 節や割れを取り除いているため、品質が安定している
- 幅・厚さ・長さを自由に決められる
- 無垢材に比べて、価格が安い傾向にある
- 無垢材のような自然由来の調湿効果は得られない
- 天然木そのものの木目や美しさ、風合いに欠ける
- 接着剤の劣化により、接着部の耐久性が低下する場合がある
- 接着剤に含まれる化学物質によって健康被害を引き起こすリスクがある
集成材は、無垢材に比べて「品質が安定している」「価格が安い」「サイズのバリエーションが多く、好みのものを選びやすい」のが大きなメリットです。
一方、デメリットには「無垢材のような木の風合いは感じられない」「調湿効果など天然木由来の効果は得られない」「接着剤の安全性が懸念される」などがあげられます。
集成材の価格の相場
ホームセンターで売られている集成材のほとんどは造作用で、DIYの材料としてもおすすめです。価格は、樹種やサイズ(厚み・幅・長さ)、容積、塗装の有無などによって変動します。
一例として、DIY初心者でも扱いやすい樹種の集成材の価格帯を以下にまとめました。
| 樹種 | 特徴 | 25×250×1000mm (税込/円) | 25×600×1800mm (税込/円) |
|---|---|---|---|
| スギ | 軽くて柔らかいため、初心者でも扱いやすい。用途:棚、家具など | 3,040円 | 15,420円 |
| パイン | 価格が手頃。明るくナチュラルな色合いが人気。用途:家具、カウンターなど | 2,320円 | 11,750円 |
| ゴム(ラバーウッド) | 硬さは中程度で加工や塗装しやすい。耐朽性は低い。用途:机、椅子、カウンター、テーブルの天板など | 2,240円 | 11,380円 |
| タモ | 均一で美しい木目と、硬くて丈夫なのが特徴。用途:家具、フローリング、スポーツ用品など | 3,830円 | 19,460円 |
| アカシア | 衝撃や曲げに強い。心材は茶色、辺材は茶色で木目がはっきりしている。用途:学習机、ダイニングテーブル、テーブルの天板など | 2,530円 | 12,850円 |
参照:木材通販のマルトクショップ「最新版!木材価格別ランキングをご紹介」
集成材の強度と耐久性
集成材はJAS(日本農林規格)に基づいて、品質が保証されており、接着するラミナの材質や枚数などによって強度が変わります。集成材の強度は、製品に貼られているJASシールの「E」と「F」の値で判別できます。
- E(ヤング率)…たわみにくさの指標を表し、数値が高ければ高いほどたわみにくい。
- F(曲げ強度)…曲げに対する強度を示した数値で、高ければ高いほど折れにくい。
つまり、Eの値が大きいほど変形しにくく、Fの値が大きいほど強度が高い木材です。
また、集成材に使用される接着剤の性能は、3つの使用環境で区分されています。
| 使用環境A | ・屋外での利用、かつ構造部の火災時において高度な接着性能が要求される環境 ・高度な耐水性・耐候性・耐熱性が要求される環境 |
| 使用環境B | ・使用環境Cに加え、高度な接着性能が要求される環境 |
| 使用環境C | ・屋内での利用に対応し、接着剤の耐水性・耐候性、または耐熱性について通常の性能が要求される環境 |
まとめ
DIYや住宅建材に人気の集成材には、構造用・造作用をはじめ、用途や見た目に応じた多様な種類があります。
安定した品質とコスパの良さが魅力ですが、接着剤由来のリスクもあります。特徴や選び方を把握し、目的に合った集成材を選びましょう。
木に関するお悩みは「旭川木工センター」にご相談ください!

「旭川木工センター」は、家具・建具・クラフト・木材・木工機械のメーカーが集まったプロ集団のコミュニティです。
合板加工、建具、家具など、さまざまな木工職人が所属する11社の中から、お客様の「木」に関するお悩みやご要望に応じて適切なサービスをご紹介します。
- カスタマイズしたい
- 家具を製作・注文したい
- 家具を修理したい
- 木材を探している
- 技術講師を頼みたい
こんなお悩みをお持ちの場合には、ぜひ「旭川木工センター」にご相談ください。